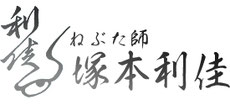ねぶた師
塚本利佳の取り組み
アイデア一つで破棄されるものが新たな付加価値を持ち、生まれ変わり、手に取る人の宝物になる
華やかなねぶた祭の裏側で破棄されるねぶたは青森市の課題ともなっていることはご存じでしょうか?
下絵の構想からを含めると約1年をかけて制作されるねぶた。
祭り期間はわずか6日間。
入賞しなければその役目を終え、すぐに取り壊されてしまいます。
ねぶた師を含め、ねぶた制作に携わる者はその様子を見守ることもあれば、つらすぎるその光景に目を伏せてしまうこともあります。
それは制作に真剣に向き合っていればいるほど苦しいものです。

役目を終え、取り壊されるねぶた
アップサイクルは本来であれば破棄されてしまうモノが新たな付加価値を持ち、生まれ変わることです。
役目を終えたねぶたも手に取る人の宝物になるのなら素敵なことですよね。
現在、私の制作団体である青森大学・青森山田高等学校では「SDGsプロジェクト」と称し、剝がされたねぶたの和紙を使用し
団扇やポチ袋の作成を授業の一環として取り組んでおります。
また私は昨年、SNSを通じてお会いした方からご連絡いただき、アクセサリー制作の一部に剥がされた和紙を活用していただいております。
剥がされたねぶた和紙の使用は、今後も様々な可能性を秘めていると感じています。
そして制作者は自分の制作したねぶたが誰かの宝物になると思えば、壊されることも悪くないと思える。次の制作にまた命を懸け、新たなねぶたを作り出すのです。
2023年の初陣に合わせて行われたアップサイクル。廃棄されるコスメを使用した色材の活用
廃材となったねぶたを使用したアップサイクルはもちろん大切なのですが、制作段階から環境にやさしい素材や方法を選択することもまた、青森ねぶたの未来を考える上で大切になるのではないかと考えています。
そこで出会った廃棄コスメ(※)を使用した色材。
モーンガータ様から色材をご提供いただき、2023年の初陣からねぶたの色付けに活用させていただいております。
※化粧品メーカーより排出される、中身は異物混入等ではなく、ある一定の品質に辿り着かなかったもの。製造工程や調合において本来の色を製造できなかった場合、破棄されてしまう。
私がいてもいなくても

ねぶたはこれまでも竹が針金に変わったことや電気も蝋燭から電球やLEDに変わることで、様々な表現が出来るようになってきました。
伝統的な技術や材料を大切にしながら、色材にとどまらず新たな理想や発想を持ち、歩みを止めないこと。
ねぶたは制作している者だけのモノではありません。
運行をする人、囃子方、跳人、観てくれる人、宝物を手に取ってくれる人。
一見ねぶたとは全く関係がないと思っていても、遠くにいても、どこかで繋がり支えあって今のねぶたがあります。
私がいてもいなくても、ひとりひとりの支えがこれからのねぶたを発展させていくのだと思っています。
塚本利佳
©Rika Tsukamoto ねぶた師 塚本利佳 公式サイト All Rights Reserved